公益社団法人 全日本病院協会
織田良正さん
医師/社会医療法人 祐愛会織田病院 副院長 兼 総合診療科部長
【PROFILE】
おだ・よしまさ
2007年、佐賀大学医学部卒業。2009年、佐賀大学胸部心臓血管外科入局。関連病院にて経験を積み、日本外科学会外科専門医資格取得。2014年、実家である織田病院に入職し、循環器診療を担当。2015年10月、MBC(メディカル・ベースキャンプ)を立ち上げ、専従医師となる。2017年、佐賀大学医学部附属病院総合診療部医員。2018年、同助教。2019年、織田病院総合診療科部長に就任し2022年より同副院長を兼務。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・内科指導医、日本外科学会認定登録医、日本病院総合診療医学会認定医・特任指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医。佐賀大学医学部臨床教授も務める。
退院直後の訪問サービスで高齢患者の在宅生活と地域医療を支える
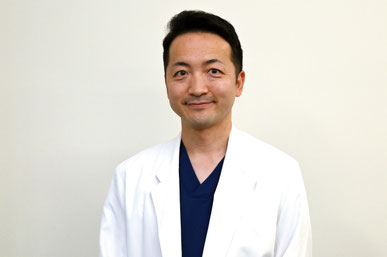
地域の急性期医療を幅広く担う社会医療法人祐愛会織田病院を経営する織田家の15代目。医師になって8年目に織田病院に入職し、退院直後の患者に病院から訪問サービスを提供し、在宅生活へのスムーズな移行に誘うMBC(メディカル・ベースキャンプ)の立ち上げを担い、自らも在宅医療に着手。その後、母校の総合診療部で学び直し、外科と内科、2つの専門医資格を持つ稀有な医師として織田病院に復帰した。現在は副院長として医療経営に携わりつつ総合診療科医師として外来・救急・訪問ともに診療活動も続けている。
外科と内科、2つの専門医資格を地域医療に生かす
――元々は心臓血管外科医でしたが、在宅医療に携わったのをきっかけに、あらためて大学の総合診療部で学んだそうですね。
織田 心臓血管外科を選んだのは、地域(佐賀県鹿島市)の急性期基幹病院として、日々、たくさんの救急患者さんを受け入れている織田病院にとって、救急対応に困らないスキルを習得するという意味でも重要な分野であり、診療科の選択時には私の父である織田正道理事長の後押しもありました。。当院の循環器科には、ロールモデルとなるプライマリ・ケアから高度な治療までトータルにこなす心臓血管外科医が勤務しており、私自身も、その医師を通して、心臓血管外科は全身を対象としていて地域医療への貢献度が高い診療科だと感じましたし、今でもこの科を選んで良かったと思っています。
臨床研修後は複数の関連病院で経験を積み、佐賀県立病院好生館(現佐賀県医療センター好生館)で外科専門医資格を取得した後、医師になって8年目の2014年、32歳の時に医局から派遣のかたちで織田病院に赴任しました。「若いうちに地域医療を経験しておくと良い」という理事長からのアドバイスを受けてのことでした。その後は内科、外科含めて循環器診療、救急医療に打ち込み、約1年半の間に高齢者を中心にたくさんの患者さんを診させていただきました。
次に着手したのが「メディカル・ベースキャンプ (Medical Base Camp:MBC)」の立ち上げです。MBCは、当院を退院した直後の患者さんを対象に、病院スタッフによる訪問サービスを実施し、安心して自宅で暮らしていただけるように支えていく取り組みです。私はMBC開設と同時に専従医師として着任し、特に佐賀大学から派遣された総合診療科の若手の医師たちにも助けてもらいながら、スタッフと一緒に退院後の訪問診療やケアに力を注ぎました。このMBCの活動を通して感じたのが、在宅患者さんを診るには総合診療の知識が不可欠ということでした。そこで、総合診療をきちんと学ぶために、母校の総合診療部にお世話になることにしたのです。
――佐賀大学医学部附属病院総合診療部は、歴史ある診療部門だそうですね。
織田 国立大学医学部附属病院の総合診療部門としては全国で初めて、1986年に設置されました。私は2017年に医員として入職し、翌年には助教となって後輩の育成なども行いながら、2年間みっちり総合診療を勉強させていただきました。この間に認定内科医の資格を取り、最終的には織田病院に戻ってから、医局のサポートのもとで学位まで取得させていただきました。
総合診療科部長として織田病院に戻ったのが2019年。2022年からは副院長を兼務しています。大学を離れてからも勉強を続け、2024年には総合内科専門医・内科指導医の資格を取得しました。専門医資格を取るには研修体制が整った環境が必要であり、外科と内科、両方の専門医を取得するのはなかなか難しいことです。それができたのは恵まれた環境や出会いがあったからだと思っています。
退院直後の2週間をMBCが支え、在宅生活にソフトランディング
――MBCを立ち上げた背景と仕組みをご紹介いただけますか。
織田 当院のある佐賀県南部の鹿島市にはいくつかの病院がありますが、公立・公的病院はなく、民間病院が役割分担をして地域を支えています。その中で当院は急性期病院としての役割を担っています。ところが2012年頃、猛スピードで進む少子高齢化により85歳以上の比率が非常に高くなってくると、明らかに患者さんの様相が変わってきました。75歳以上の人が増加した頃は比較的退院がスムーズだったのですが、多くが85歳以上となると認知症の発症率も高くなるうえ、配偶者も高齢であるなど退院が滞るケースが増えてきたのです。一方で救急搬送される高齢患者さんも増え、そのためのベッドの確保は不可欠です。高齢の患者さんにも安心して自宅に帰っていただき、退院後も安定して在宅療養をしていただくための仕組みづくりが急務となりました。
その仕組みとして最初に導入したのが多職種協働フラット型チームで、病棟に全職種を配属し、高齢者が抱えるすべての問題を皆で解決するシステムをつくりました。これが2013年。さらに、退院後の自宅生活での問題にまで介入できる方法として考えたのがMBCです。高齢の患者さんは退院すると入院中に受けていたケアが途切れることで状態が悪化しやすく、再入院となるケースも少なくありません。このことがベッドの不足を招き、また、患者さん自身やご家族、在宅医療を担当する地域の医療・介護関係者の不安の原因にもなっていました。そこで特に状態が不安定な退院直後の2週間を目処に、病院のスタッフの訪問サービスによってケアを継続し、その間の生活を支えることで、入院から在宅にソフトランディングしていただく流れをつくりました。
――訪問サービスのベースとなる場所が院内にあるのですか。
織田 MBC立ち上げと同時に院内の連携センターに、専従医師である私と、訪問看護師、リハビリ職、介護福祉士、ケアマネジャー、ソーシャルワーカーなど多職種を配置し、ここを拠点としました。連携センターには60インチの大画面が並び、MBCが関わっている在宅患者さんの状態をモニタリングしています。患者さんには必要な機器を貸し出してあり、何かあったらビデオ通話で確認できます。また、訪問サービスに出ているスタッフの居場所をスマートフォンのGPSで把握することで、患者さんの近くにいるスタッフが駆けつけることもできるようになっています。カルテのクラウド化や遠隔診療のシステムも完備し、状況に応じて患者さんをサポートしています。今では、当院の連携センターが地域のスタッフステーション、道路が廊下、患者さんのお宅が病室、というふうに、地域全体を1つの病院と捉えられるような環境が整っています。厚生労働省が提唱する「2040年に向けた地域の医療提供体制のイメージ」を具現化できていると言えると思います。
――地域包括ケアシステムが鹿島市ではすでに構築できているのですね。
織田 はい、今後さらに行政との連携などをより強化する必要があると思いますが、概ね整っています。

目指すは「究極の地域密着型病院」
――織田病院の取り組みは1つのモデルケースとして注目されていますね。
織田 おかげさまで厚生労働省の「かかりつけ医機能に関する取組事例集」に好事例として紹介されたり、講演を依頼されたりすることも増えました。少しでもお役に立つことができればと思い、お引き受けしています。
――全日本病院協会や在宅療養支援病院連絡協議会でも啓発活動などをされていますか。
織田 私の経験や取り組みを参考にしていただけるのであれば引き続きぜひ協力していきたいと思っています。私自身は、こういう医療がしたい、といった強い思いは特になく、MBCをつくったのも、在宅医療に取り組んだのも、それが地域にとって必要だったからです。高齢の患者さんに対して医師一人ができることは限られています。だからこそ、自分が何をしたいかではなく、患者さんが何を求めているかを汲み取り、それに応えることが大事だと思っています。地域での取り組みを積み重ねた結果、その取り組みが全国的な団体活動に繋がり、同じような環境で日々頑張っている全国の病院の参考になるのであれば、これ以上の喜びはありません。
――目指す病院像のようなものはありますか。
織田 言葉で表現するなら、「究極の地域密着型病院」を目指しています。当院は、地域医療の最前線でありながら、佐賀大学医学部附属病院地域総合診療センターが設置されるなど、大学病院とも連携し最先端の地域医療を提供しています。現在は鹿島市をメインのエリアとしていますが、今後、少子高齢化が進行する中で診療所の減少などにより、もっと広い範囲をカバーする必要が出てくるかもしれません。そうした時代の変化を見据えつつ、地域のニーズを把握しながら、求められる医療を提供していきたいと思っています。自宅でも病院でも施設であっても、地域の人々が最期まで、慣れ親しんだコミユニティの中で暮らしていけることを大事に考えていきたいと思います。
――日本在宅ケアアライアンスに期待することがありましたらお願いします。
織田 在宅医療が今後ますます求められてくるのは必至ですし、関連団体が結集してこれからの在宅医療のあり方を考え、発信していくことはとても大事だと思います。これからも有識者の皆さんの知見をお示しいただけたらと思います。

サッカーの戦術に多職種連携を重ねる
――余暇はどのように過ごされていますか。
織田 何かしら予定が入っていることが多いですが、スポーツ観戦が好きです。小中高大と学生時代、何かしらスポーツをしていました。大学ではラグビーをしていたのもあってラグビーはよく見ますし、サッカー、野球、バスケット、スポーツはなんでも好きです。最近、特に好きなのがサッカーの戦術動画。サッカーにはいろいろなポジションがありますが、各ポジションの役割やフォーメーション、戦い方はチームごとに違います。そのあたりが、多職種が連携して取り組む地域医療に似ていて、見ていてとても参考になります。一方で、野球はピッチャーとバッターの1対1の勝負の中でどんな駆け引きをしているのか、何か診療に繋がるようなところもあり面白いです。箱根駅伝も小さい頃から見ています。鹿島市には箱根駅伝のチームが毎年合宿に来るのですが、一目見るだけで長距離選手と分かります。私自身は運動がリフレッシュではなく、疲れを残すだけのものになりつつあり、すっかり運動しなくなりました。(笑)。
――最後にあらためて病院経営についての考えや今後の展望をお聞かせください。
織田 近年、病院経営の厳しさがさまざまな方面から言われています。新型コロナウイルス感染症の流行による打撃、人材不足、物価高・・・確かに経営課題は山積みで、ネガティブな話題ばかりのようにみえます。。ただ、医療というのは人が生きる上で不可欠で、多くの人に感謝されるやりがいのある分野ですから、私自身は医師としてもリーダーとしても、地域のためにより良い取り組みをしていけたらと思っています。

取材・文/廣石裕子
